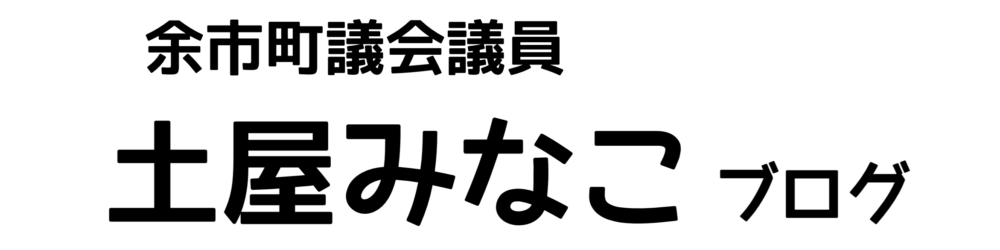2月8日(木) 余市町でも “群来” が確認されました。
(今年の写真がないので、去年の山本議員が撮った写真を使いました。)
群来とは、産卵のために大量のニシンが海岸に押し寄せ、オスの精子によって海が白濁することです。
かつて余市町には毎年何万トンものニシンの大群が押し寄せ、明治・大正の最盛期には「網をひと起こし千両万両」と呼ばれるくらいに、現代に換算すると春先の3ヶ月だけで数億円もの利益を生みました。
しかし、昭和29年を境に群来はピタリと途絶え、ニシンは姿を消し、「資源が枯渇してしまったのでは…」という見方が常識となっていました。
そのニシンの群来が、50年もの時を経て見られるようになりました。
ソーラン節発祥の地でもある余市町にとって、やはりニシンは特別な魚だと思います。
「群来た」と聞くと、心が躍るし、すごく嬉しい気分になります。
今年のニシンとホッケを頂きましたので、今回は切り込みを作ることにしました。
ニシンが群来ると、そのニシンの卵を追ってホッケも大量に来ます。

ニシンの切り込みの作り方
まずウロコと頭を取って、卵(数の子)、白子、内臓を取り、3枚におろします。
数の子と白子はバットに塩水を作って入れておきます。


3枚におろした身のお腹の骨を削いで取り、ぶつ切りにし、血抜きのために水に浸して寒い所へ置きます。
血抜きは、最低でも1日に2〜3回水を替え、3日間ほどかけてしっかりと血抜きします。
念入りに血抜きすることで、出来上がりがピンク色にならず、白くキレイに出来ます。

今回は、食べ応えがあるように、大きくぶつ切りにしてみました。
血抜きが出来たら軽く重しをしてしっかり水気を切り、重量の10%の塩とこうじをそれぞれ入れ、鷹の爪(お好みで)も入れて (砂糖か味醂も少々、お好みで入れても良い) 寒いところに置いて発酵させていきます。

毎日、1回は空気を入れるようにかき混ぜます。
10日くらいで食べられると思いますが、1ヶ月以上( 2〜3ヶ月)つけた方が塩の角がとれてこうじの力で柔らかくなり美味しくなります。
食中毒菌も変化をしているので一概なことは言えませんが、基本的な部分で言うと、塩分6〜7%でほとんどの細菌は死滅します。
こうじ菌とカビ、白カビなどは塩分15%まで活動出来ます。
元々毒を持った食中毒菌は死滅しても毒素は残ります。
ウイルスは付着している状態だと1週間くらいで死滅します。
数の子は塩水から取り出し、塩をまぶして2日くらい、寒いところへ置いておきます。
塩は適当に振りますが、後で塩抜きするので多めに (多すぎて失敗することはない) 振ります。

すると柔らかかった数の子がバキバキに固くなっています。
この数の子の薄皮を剥いて、真水ではなく少し塩を入れた薄い塩水で塩抜きします。
水 (薄い塩水) を替えながら2日ほどかけて、塩抜きします。
間に残っている血や汚れも、この過程でキレイになっていきます。
2日ほど経ったら、つまようじで間に残っている薄皮を取ります。
これを取らないと生臭みの原因になることもあります。
最後にもう1日、薄い塩水で塩抜きして、「黄色いダイア」とも呼ばれる数の子の出来上がりです。

私はこれをぶつ切りにして、切り込みに加えます。
切り込みに入っている数の子は美味しい。(o^^o)
今回はホッケも同じような過程で、切り込みにします。
焼いても煮ても美味しい栄養豊富な春告魚、旬のニシンをたくさんいただきたいと思ってます。